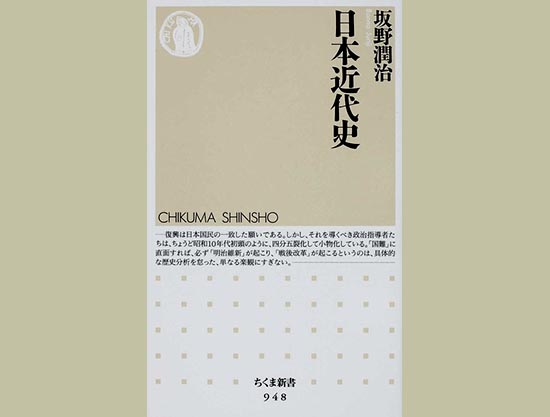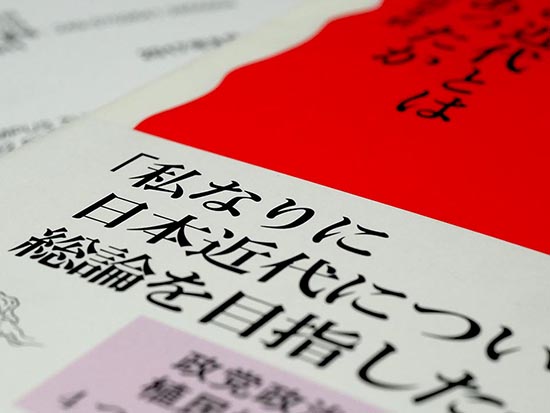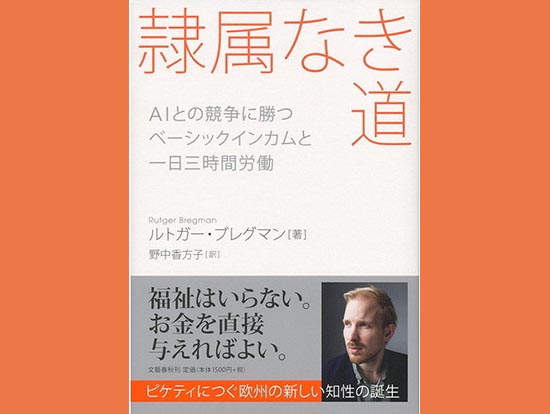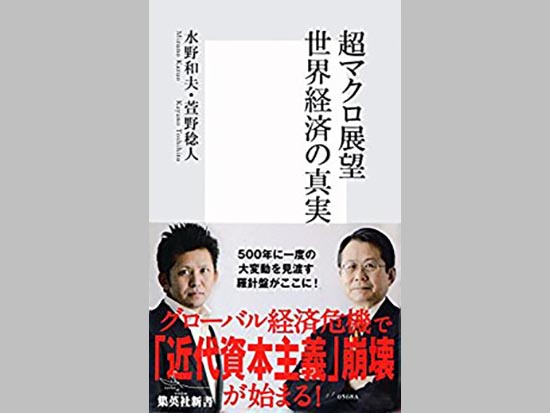『昭和維新試論』
橋川文三 著
2013年刊 講談社学術文庫
明治の終わりから昭和の初めにかけて、
戦争に向かって流れていく時代の意識を
当時を生きた個別の人物に寄り添うように分析した評論である。
雑誌連載をもとにして、最後まで仕上げることなく
著者が亡くなっていることもあり
全体としてのまとまりにはやや欠ける気はするが、
取り上げられている個々の人物への思い入れは強く感じられる。
特に渥美勝などに対して感じられる共感は
客観的な人物評を超えて強引な気がするほどで、
著者はそこに自己の深い心理を勝手に重ねているように思う。
しかし著者が感じているそれぞれの人物への共感は、
この評論にリアリティと迫力を与えている。
歴史的事実としてのリアリティではなく、
そこにそんな人物が確かに存在したのだというリアリティである。
そしてそんな人々がいたことをリアルに感じることで、
その時代をもリアルに感じることができるのであり、
その時代が現在まで続いていることを理解できるのである。
それは戦前も戦中も戦後も今もずっと
果てしなく続いている
苦悶と疑問と愚問の近代という世界である。