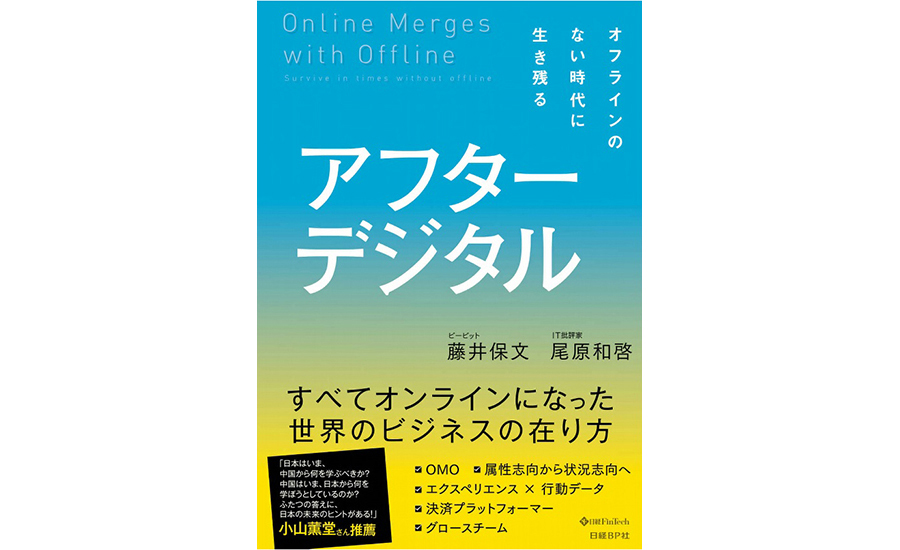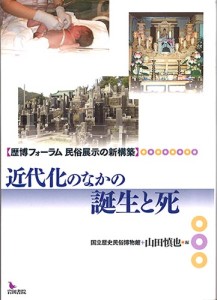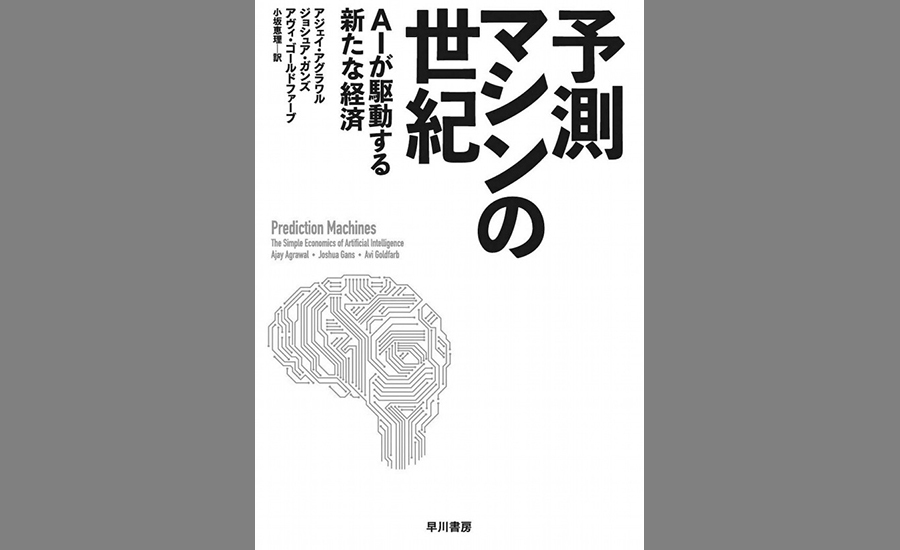
これは経済学の視点か見たAIという話で、質・量ともに充実した極めてクールな内容です。
なぜ、現在がAIの時代になりつつあるのか?
その答えは経済学的には至ってシンプル。
<計算がものすごく安くなったから>です。
これが重要で、すべてはこれに尽きる。
これは電気を例にとれば明らかで、蛍光灯をひとつ点けるのに10分間で100万円必要なら世界の夜は今も暗闇のままでしょうけれど、電気が安くなったから電気代を気にせず灯りを点けるし、冷蔵庫や洗濯機やおもちゃから列車まで電機は様々なものに使われるようになった。
膨大な計算能力を必要とするAIも、計算単価がとてつもなく安くなったからどこにでも使われるようになってきたということです。
その<安さ>こそが世界を根底から変えてしまうのです。
移動や通信やエネルギーのコストが世界を変えてきたように。