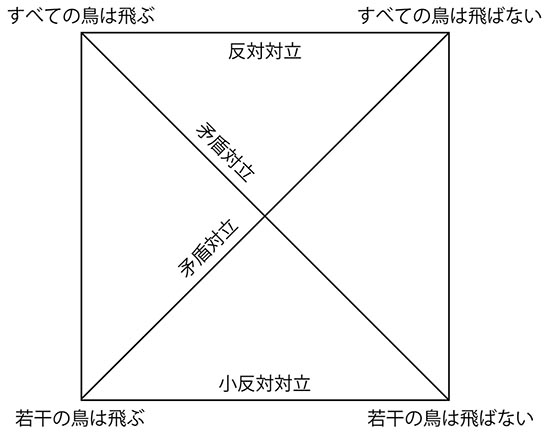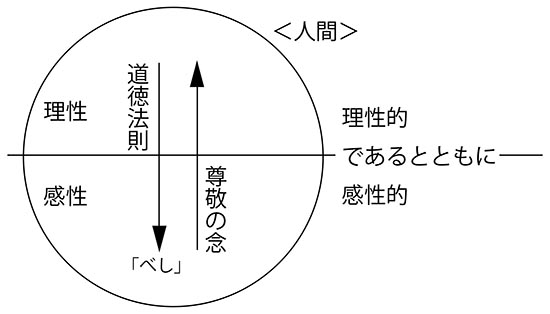『カント入門』
石川文康 著
1995年刊 筑摩書房
のどにひっかかりそうな小骨をきれいに取り除いて、
おいしいところを無駄なく丁寧に盛り付けた感じのカント入門書。
何しろ理性を批判しながら、
最終的には理性による信仰へとたどり着くという
アクロバティックな展開である。
それをなじみのない哲学用語を用いながら、
わかりやすくかつ噛み応えのあるまとめとしている。
コンパクトではあるが、コンパクトにまとめることの苦労が
伝わってくる労作である。
以下、本文より・・・
第1章 純粋理性のアイデンティティー
1 カント哲学をつらぬくもの
・常識的には真理や善のより所であるはずの理性が
人間を欺く本性をもっている
・これによって彼は、知性にではなく経験に真理のよりどころを求める。
知性はなるほど世界を映しだす鏡かもしれない。
しかしそれは歪んだ鏡であり、
物をみずから着色して映しだす鏡ですらある、と。
・「真理の探究」を旨とする哲学は
どうしても仮象批判の形をとらざるをえない。
・批判哲学の面目は、また批判哲学の名称の由来は、
合理性そのものに対する疑いにある。
・理性固有の仮象、それをカントは
―感覚的・光学的錯覚等、経験的仮象と区別して―
「超越論的仮象」と呼んだ
・合理性が合理性に反するというパラドックスが存在するということである。
それは、理性が理性自身の法則にのっとって推論を進めた結果、
理性に反する結論に到達するという皮肉な現象である。
・「人間の理性はある種の認識において特殊な運命をになっている。
すなわち、理性が退けることもできず、
かといって答えることもできないような問いに
煩わされるという運命である」
←『純粋理性批判』
・そのような相反する命題のペア(一対)を、
カントは「二律背反」すなわち「アンチノミー」と名づけた。
アンチノミーこそが理性批判の発端である。
2 純粋理性のパラドックス
―アンチノミー(二律背反)
・理性は自分の能力だけで、与えられた物事を超えて、
その背後や根拠にも合理性を求め、
一切の物事の根本にどこまでもさかのぼろうとする傾向をもつ。
理性のこのような傾向が学問となったのが
「形而上学」(物事の背後にある原理を追求する学問)である。
そのような傾向から、理性はついに
「絶対」とか「究極」とか「完全」といった概念を生みだす。
・それゆえに、これらの概念は一般に、
理性概念、すなわち「理念」と呼ばれる。
・伝統的形而上学はそれを反映して、
「神」、「自由」、「魂の不死性」を代表的テーマとする。
・第一アンチノミー
テーゼ:世界は空間・時間的に始まりを有する(有限である)
アンチテーゼ:世界は空間・時間的に無限である。
・第二アンチノミー
テーゼ:世界における一切のものは単純な部分から成る。
アンチテーゼ:世界における合成されたものは単純な部分から成らない。
単純なものは存在しない。
・第三アンチノミー
テーゼ:世界は自由による因果性もある。
アンチテーゼ:自由なるものは存在せず、
すべて自然必然的法則によって起こる。
・第四アンチノミー
テーゼ:世界原因の系列の中には絶対的必然的存在者がいる。
アンチテーゼ:この系列の中には絶対的必然的存在者はいない。
そこにおいてはすべてが偶然的である。
・それは要するに「ある」と「ない」の問題、
とりわけ「ある」と「ない」の多義性の問題に帰着する
3 「独断のまどろみ」からの目覚め
・ヒュームによれば、因果律はアプリオリな客観的法則ではなく、
単なる連想の産物、すなわち観念の主観的な結合にすぎないという。
因果律批判の因果律批判たるゆえんである。
第2章 カント哲学の土壌と根
―批判哲学への道
1 証明不可能な根本真理
―伝統的合理主義のまがり角
・魂は広がりをもたない、
すなわち空間的に合成されたものでなく、
単純な実体である。
合成されていない単純なものは、分解されえない、
すなわち消滅しない。
ゆえに魂は不死である。
←メンデルスゾーンの証明
・哲学においては定義は出発点ではなく、
むしろ目標とすべき終着点なのである。
・すなわち、カント哲学は、
後に批判哲学と呼ばれるにせよ理性批判と呼ばれるにせよ、
そもそも出発点からして、定義不可能な根本概念と
証明不可能な根本真理を相手どる営みであった
・それが根本真理であるがゆえに、
どうしても照明不可能である
2 「哲学者カント」の誕生
・世界概念の哲学とは「人間理性の本質的目的」、
「究極目的」を目指す哲学、「人間の使命」にかかわる哲学である。
・すなわち、哲学者カントが誕生したとき、
彼の哲学概念は学校概念から世界概念に一転したのである。
第3章 迷宮からの脱出
―第一アンチノミーの解決
1 仮象を見ぬく視座
・「[われわれの]認識が対象に従うのではなく、
むしろ対象の方がわれわれの認識に従わなければならない」
(『純粋理性 批判』序論)
・2 「黎明」から「大いなる光」へ
―第一アンチノミーの解決
・それ自体として空間・時間的な量をもたないものに、
有限か無限かということを問題にしても、どちらでもない。
それにもかかわらず、どちらかに決すれば、
それはいずれにせよ偽となる。
ゆえに、アンチノミーの両命題はいずれも偽である。
・「四角い円はまるい」という命題と、
「四角い円はまるくない」という命題は
たがいに対立しあっているが、両方とも明らかに偽である。
ここからわかる重要な指針は、
対立しあう二つの命題がともに偽の場合、
そもそも両命題の共通の主語概念が
不合理をはらんでいるということである。
・空間・時間は世界全体の客観的条件ではない。
要するに、世界の絶対量は「ゼロ」である。
・空間・時間は世界全体の客観的条件ではない。
要するに、世界の絶対量は「ゼロ」である。
・絶対的全体としての世界というものを、
われわれは空間的にも時間的にもとらえることはできないのである。
それをわれわれは、単に思いみることができるだけである
(「思う」ということには、じっさいの空間も時間もいらない)。
・カントは空間と時間が主観(感性)の性質であって
物それ自体の性質ではないことを、間接的に証明した。
そしてこの主張を彼は、「超越論的観念論」と名づけた。
・発見とは既成のものの見方(価値観、世界観)を打破し、
そこに潜む先入観を見抜き、対立を超えて新たにして
第三の価値を見いだすことである。
・空間と時間の支配する領域、それを「現象」という。
そしてこれのみが、われわれにとって有意味な認識の領域にほかならない。
・空間と時間がわれわれ認識の主観の形式であることから、
同時に、それらは存在の全領域にわたるものではないことになる。
そのことはすなわち、空間と時間のおよばない存在領域があること、
少なくともそれを想定しなければならないことを必然的に含意している。
それをカントは「物自体」と呼んだ。
要するに、物のありのままの姿である。
・現象としての物を「現象体」とも言うのに対して、
物自体はまた、単に想い見られるだけの物であることから、
「可想体」とも言う。
また前者が感性の形式(空間・時間)によって成りたつ世界であることから、
「感性界」と呼ばれるのに対して、
後者は、それらの形式から解放されている、
あるいは超えているという意味で、「英知界」とも呼ばれる。
→カント哲学のドグマ、「躓きの石」とも
第4章 真理の論理学
―経験世界の脈絡
1 有意味で必然的な認識
―アプリオリな総合判断
・直観こそが認識の実質を提供する条件
・総合判断が「総合的」と呼ばれるのは、
右に述べたように単に主語に含まれていない概念を
主語と総合するからというにとどまらず、
より積極的には、概念と直感の総合を実現するから、
と言うことができるであろう。
・真に学的判断はすべて
アプリアリな総合判断であることが予想される。
2 人間の思考の根本枠
―カテゴリー
・人間の知性―これは従来、悟性と訳されてきた―も
それ固有の枠組みをもっていなければならない。
それをカントは「純粋知性概念」、
また彼固有の(アリストテレスに倣った)名称で
「カテゴリー」と呼んだ。
←直観(空間・時間)に対する概念の側のエレメント ←「総合判断」=「直観」+「概念」
・人間の認識は感性と知性の協同作業である。
すなわち、空間・時間という窓口を通じて与えられた素材が、
カテゴリーによって処理されてはじめて、一定の意味ある認識が成立する。
・因果性もじつはそのようなカテゴリーの代表例
・カントはそのような判断形式を12に還元し、
それに対応してカテゴリーを全部で12個発見した。
この作業をテゴリーの「形而上学的演繹」と言う。
・知性は現象や対象の差異に応じて、
そのつど12のカテゴリーのいずれかを組みあわせて、それらを把握する
・カントの場合、「アプリオリ」とは「経験に先立つ」
すなわち「経験に由来しない」という意味を出ない。
・カントが第三項として導入した自然法用語「根源的獲得」は、
一切の先なる所有権を、また先なる根源を前提しない概念である。
それは知性がその事故活動によって知性自身から獲得したという意味である。
・カントが樹立したのが自己意識の原理である。
それは、「統覚」と呼ばれる不動の自我にほかならない。
「統覚」と呼ばれたのは、それが、われわれの一連の知覚を、
当の知覚レヴェルを超えて、
一定の合理的脈絡に統一する能力だからである。
・刻一刻どんなにことなった意識をもとうと、
わたしは別々のわたしなのではなく、
依然として同一のわたしである。
カントはこのような自己意識を、
「根源的統覚」あるいは「超越論的統覚」と呼んだ。
・同一の自己意識は、端的に「わたしは考える」という
命題であらわされる純粋な意識になる。
・カントは統覚の総合的統一を、人間の認識の最高の原理
あるいは知性使用の最高原理とする。
3 経験世界の脈絡
―アプリオリな総合的原則
・「ファジー」とは「あいまい」を意味する、
と受けとられているが、じつはそうではなく、
むしろその反対であり、
この概念の真の意味における「厳密性」を意味している。
・無限の度を有するものは、
きっぱりと「イエス(ある)」か
「ノー(ない)」かの二値で言いあらわしきれず、
つねにどの程度そうなのかが問題になったり、
どちらでもない場合もあるからである。
・「経験一般を可能にする条件は、
同時に経験の対象を可能にする条件である」
←『純粋理性批判』「原則論」
・これをもって、伝統的形而上学のテーマである
「神」「自由」「魂の不死」は学問としての形而上学から
完全に排除されることになる。
これらに関してはいずれも、「いつ」「どこ」が確定できないのである。
第5章 自然因果の彼岸
―自由と道徳法則
1 自由の保証
・自由とは物事の第一にして絶対的始めである。
それは、一切の先なる原因を前提しないという意味である。
「自由」という日本語は「ミズカラ(=自)ニヨル(=由)」
という意味である。
・この第一の始めをカントは自由と呼び、
それが感性人における出来事の究極原因となってはたらくことを
「自由による因果性」と呼ぶ。
・カントは自然因果の支配を現象界に制限し、
自由のありかを英知界に配することによって、
両者が共存する可能性を確保する
2 道徳的仮象と真の道徳
―条件つき命法と無条件の命法
・「この世の中でも、この世の外でも」
善として通用するものは善意志をおいて他にない
・善意志は義務という概念に凝縮している
・善を実現するためには、少なくとも有限な人間にとっては、
大なり小なり義務感(快感とは逆の感情)が前提され、
これをもって臨む以外にはないのである。
・無条件な命法とは、文字どおり、無条件に、
すなわち仮言命法に見られたような条件句をともなわずに、
端的に「嘘をつくべきでない」、と命じる命法である。
無条件とは絶対的という意味である。
・カント自身、仮言命法をはっきり「道徳性のにせの原理」と呼んでいる。
・カントはこの黄金律を、「取るにたらない言辞」と一蹴
→「もし自分がなにかを欲しないなら、それを他人にも為すべきでない」
→「自分が他人にしてほしいように、他人にもしなさい」
・カントの批判的倫理学は、理論哲学においてそうであったように、
一貫して仮象批判として遂行されていた
・それにもかかわらず「(ローマへ戻って)わが民とあるべし」、
という明らかな定言命法の実例
3 道徳法則への尊敬の念
・尊敬の念とは「自愛の念を挫く感情」
4 定言命法の定式
・「汝の意志の根本指針がつねに同時に普遍的立法の原理となるように行為せよ」
これは定言命法の根本方式である。
・「汝の行為の根本指針が、汝の意志によって、
あたかも普遍的自然法則となるかのように行為せよ」
(定言命法の第一方式)
これは一般に「自然法則の方式」とも言われている。
・「汝自身の人格にある人間性、およびあらゆる他者の人格にある人間性を、
つねに、同時に目的として使用し、
けっして単に手段として使用しないように行為せよ」
(定言命法の第二方式)。
・それらを担った存在者(人格)が道具とちがうのは、
手段としての意味をもつだけでなく、
「つねに同時に」目的そのものとしても存在する
・「意志が・・・自己自身を同時に普遍的に立法的と見なしうるような、
そのような根本指針にのみしたがって行為せよ」
(定言命法の第三方式)。
5 「天におのれを懸けるものなく、地におのれを支えるものなし」
・カントは
「天におのれを懸けるものもなく、地におのれを支えるものもない」
状態におちいる。
しかし同時に
「それにもかかわらず、哲学は確固たる地位を確保しなければならない」
という強い自覚をもつ。
・「自由は道徳法則の存在根拠であり、道徳法則は自由の認識根拠である」
(『実践理性 批判』序文)
・われわれにでき、また為すべき唯一のことは、幸福になることではなく、
ただ道徳性(徳)の研鑽によって幸福に値する人間になることである。
・幸福は「希望」に属する問題であり、宗教に託される以外にないものである。
そのとき、希望は「信仰」という意味になる。
・宗教はあくまでも道徳によって条件づけられるのであって、その逆ではない。
・人間の本性が完全に開花すれば
「王権ではなくて内的な良心が法と公平を管理するであろう」
・カントが道徳性に託したのは、結局は良心の支配であった。
第6章 自由と融合する自然
―反省の世界
1 目的因から合目的性へ
・これまでわれわれは因果性の概念をいろいろ考察してきたが、
せんじつめれば二つにまとめられる。
ひとつは自然の因果性(通常の因果性)であり、
これは『純粋理性批判』において確立された。
もうひとつは自由による因果性であり、
これは『道徳形而上学原論』と『実践理性批判』の要石である。
・異質なものに対して理解を示すというカント固有の啓蒙の概念
2 目的なき合目的性
・1 自分自身で考えること
2 自分自身を他者の立場に置いて考えること
3 つねに自分自身と一致して考えること
3 自然の妙技
・有機体は宇宙体系や地球のエコロジカルな体系とならんで、
カントの体系概念のモデルである
・相対的目的にせよ究極的目的にせよ、
そもそも目的という概念が意味をなすのは、
目的を設定できる存在者によってのみである。
少なくとも地上においては、そのような存在者は
人間をおいてほかにないことがわかる。
そして、定言命法の「目的の方式」が命ずるように、
人間は自己および他者を人格として、
すなわち目的そのものとして見なす存在者であった。
・自由、それはその背後にいかなる条件をも前提しない
絶対的自発性を意味していた。
ということは、逆に言えば、自由な主体としての人間、
道徳的主体としての人間こそが世界の究極目的であることになる。
単に自然的存在者としての人間ではなくて、
英知的存在者であるかぎりにおける人間が世界の究極目的である。
・それゆえカントは、
「道徳的存在者としての人間については、
人間は何のために[何の目的で]存在するのか」という問いは、
そもそも無意味であると断言する。
なぜなら、人間はすでに自己自身の内に
最高の目的を含んでいるからである。
・人間の究極目的を求めるとき、
彼自身が究極目的であるとも言えよう。
第7章 理性に照らされる宗教
1 道徳は不可避的に宗教にいたる
・「道徳は不可避的に宗教にいたる[通じる]」
・道徳は自己充足しており、道徳が道徳として存立するために
「宗教をまったく必要としない」
・宗教は道徳という条件を満たしてはじめて宗教
→道徳なき宗教は仮象宗教→仮象批判
・完全な善は徳と幸福の両方で構成されなければならない。
このような徳と幸福の一致を、カントは「最高善」と呼んだ。
・理性は道徳的主体としての人格の、すなわち魂の「不死」を要請する
・理性が自己矛盾におちいらないためには、
最高善はどうしても可能でなければならない。
そのことから理性はみずから、世界の創造者にして、
同時にとくと幸福の結合の根拠を含む存在者、
すなわち神の存在を要請する。
・幸福への希望とともに宗教は始まる
・幸福追求は、もともと純粋理性がわれわれに命じたものである。
その意味で、純粋理性こそが信仰の源である
・「純粋実践理性信仰」
2 根源悪
・悪の前提においてはじめて、道徳的陶冶という概念が意味をなす
3 理性宗教の具体相
・多くの宗教があるとうのは、じつはそう見えるだけであって(仮象!)、
正しくは多くの信仰形態があるという意味である。
それらは唯一の宗教の別々の具現化にすぎない
むすび―批判哲学の原体験
・『宗教論』においてカントは、回心を思考法の革命と呼んでいた。
それが「唯一で一回的」であることを強調していた。
・ルソー告白における回心