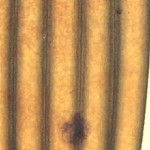『純粋な自然の贈与』
中沢新一 著
1996年 刊 せりか書房
何だかよくわからないけど印象的で美しくもあり
思わず手にとってみたくなるような
この本の表紙のデザインは、 (もちろん本のデザインとはそうあるべきだ)
紙の専門商社である竹尾が毎年行っている展示会のポスターからの引用である。
(制作は原デザイン事務所・原研哉)
原デザインのサイトによると、このポスターは
「金箔や果実の表皮などのテクスチャーを印刷プロセスに合成」して
作られたもので、
「リアルなテクスチャーを付与することで、抽象的なオブジェクトは不思議な実在を帯びてくる」
ということである。
本の表紙カバーに印刷されてしまうと、
そのテクスチャー云々というのはわかりにくくなるが、
そう言われればテクスチャーが…という気がしなくもない。
まあ、本の内容から考えて
<自然>である「果実の表皮」と人間の<文化>である「印刷」との接合点
というような意味が込められているのだろう。
株式会社 竹尾
白を基調にしたとてもきれいなサイトのデザイン
原デザイン事務所
もとになったポスターのデザイン
せりか書房
同じくこちらも白を基調にした…というか、
こんなに無愛想でいいのかといいたくなるサイトデザイン
さて、内容について
帯には
「危機にさらされる人間の霊性を
根本において支え、擁護するものとしての
『贈与の精神』を探究する、今日最大の問題にたちむかう書
マルクスとキルケゴールとモースが
一つに結びあいながら未曾有の地平を開く」
背表紙のところには
「霊性を擁護する」 とある。
大げさである。
でも、宣伝文句だからそんなものか…
とはいえ、当時の大騒ぎの時代状況から考えると
かなり煽ってる。
内容はこの帯の宣伝文句にあるような
「たちむかう」という感じではない。
よく言って<のりこえる>、いや<すりぬける>
いやいや<いいかえて、いいくるめる>くらいが妥当かもしれない。
これは本の内容を批判しているわけではない
そんなに勇ましくたちむかわなくても、
適当にすりぬけて、あっちとこっちを行き来すればいいのであるし、
拳を振り上げなくても
言い換えて認識が変わればそれでもいいということだ。
本のページをめくることで
認識のページがめくられていく。
それでいいのである。
まあ、それはいいとして
この本は
最初の「序曲」を含めて9編で構成されていて、
マルクス、キルケゴール、モース、(ここまではいいとして)
ゴダール、バルトーク、モーツァルト、シューマン、(これ全部必要だろうか)
H・ジェームズ、ディケンズと(どっちか一人でいいんじゃないかな)
いろいろな人が登場してややくどいような気がしないでもない。
二つめの「Not I,not I… 」と
三つめの「すばらしい日本捕鯨」は
読み物・エッセイとして良い出来で、
特に捕鯨の話は、自然と文化と歴史と感情が
ひとつの論理で結ばれながら展開する
美しいドキュメンタリー映像を見ているような感じである。
(もちろん現在の日本の商業捕鯨の問題とは別の話である。)
そしてメインである「新贈与論序説」も
なんか飛躍しているんじゃないかな
という感じもありながら
<三位一体>―<自由霊>―<貨幣>
<贈与・霊・無限>:<貨幣>
なんてちょっと無理やりっぽいんだけどな
とも思えながら
繰り返しと遠回しと
多少の胡散臭さで押し切っていく
なかなか見事な「いいくるめ」ぶりである。
それと、この本には
クリスマスに関する話がいくつかあって
重要なテーマになっているが
第一次大戦時の「クリスマス休戦」にはふれられていない。
しかし、それこそ
近代のエンジニア思考の果ての荒廃した戦場と、
そこに突如ブリコラージュのクリスマスの霊が現れる
という生々しい物語であり
そして現代の神話になっているものであるから、
ディケンズよりもそちら分析で締めくくってもらった方が
説得力があったと思われる。
(どこか別のところで書かれているかもしれないけれど…)
以下、本文より
「序曲」
・霊とは生命の原理そのものをあらわしている
・霊を目で見ることはできない。五感が知覚することもできない。
なぜなら、流動する霊は、五感のなかで、五感をとおして活動しているから、
五感がそれを対象化して、とらえることができないからである。
・霊についての認識は、神の観念発生などよりも、ずっと古い。
・こうして、キリスト教は、ユダヤ教の神の一体性を、打ち壊してしまうことになった。
・そこから有名な「三位一体」の思想が、つくられてきた。
これは、人類の思想史の上でも、画期的な発想である。
ひとつであった神が、ここでは三つのペルソナに分裂をおこし、
しかも分裂したままひとつに統一されるのだ。
三位一体の中で、聖霊はあいかわず、誰によっても創造されたことのない、
自由な流動性や増殖性の性質を保ちつづけた。
・カトリックは、聖霊を無視しようとした。
・カトリックの秩序に反逆して、プロテスタントの運動を開始したとき、
長いこと大地の下で眠っていた、自由な霊が目を覚ましたのだ。
マルチン・ルターは、聖書をドイツ語に翻訳するにあたって、
「聖霊(サンクト・スピリトス)」の語を、
ゲルマンの土俗にまみれた「ガイスト」の語をもってあてた。
・プロテスタントの考える、神の三位一体のうちでは、
聖霊の存在が、異常な膨張をしめすこととなった。
ポロメオの輪は、カトリックのケースの反対方向に、大きな歪みを発生させた。
そして、この歪みのなかから、自由霊が世界にみちあふれだしたのだ。
ここに、近代資本主義の矛盾にみちた成長が、開始されたのである。
貨幣は「プロテスタントの倫理」をくぐりぬけ、
聖霊の洗礼を受けることによって、堂々とみずからを増殖する資本への転化をとげたのである。
・生命の原理としての霊(ガイスト)は、死の原理を内包した貨幣を否定する。
しかし、その貨幣を資本に転化する近代の運動は、
まぎれもなく、霊の躍動とともに、開始されたのだ。
資本は貨幣に隠された死の原理を利用しながら、
その死の断片をまるで生命のように増殖させる。
・霊は生命の原理であると同時に、死者のものでもある。
近代における自由霊の躍動は、こうしてこの時代をもっとも矛盾にみちたものとして創出した。
・彼らは「ガイスト」を民族の大地につれもどそうとして、「ガイスト」自身に、裏切られていった。
・その霊はふたたび、新しい変態をとげつつある。
いまや、大地、貨幣、情報についで霊こそが人間にとっての「第四の自然」となりつつある。
だから、いま私たちにとってもっとも必要なのは、
新しい「霊の資本論」の出現なのではあるまいか。
「Not I,not I…」
・贈与がものを結びつけるエロスの力をもっているからであり、
エロスは動きながら、みずからの力を更新していくものだからである。
・それとは反対に、売買は分離の力、すなわちロゴスの力をはらんでいる。
なにかの「もの」が売られるものになるためには、まずそのもの所有者との絆が、
さまざまな意味で断ち切られていなければならないからである。
ものの売買がおこなわれるときには、売る人と買う人の間には、あらかじめ、
心理的な距離や分離の感覚が、できあがっている必要がある。
・贈与は、人を人間の世界の外に連れ出そうとしているのだ。
それは、等価性とか計算とか交換とかへの配慮を、
すべてのりこえて、あらゆるものが決定不能の状態のまま、
豊かな対話や受け渡しや消費を実現している、高次元の世界を開こうとしている。
売買は、分離するロゴスによって、「霊」を殺す。
しかい、贈与は結びあわせるエロスの力によって、
宇宙にみちる「霊」の流動を発生させ、それをますます増殖させようとしているのだ。
・哲学は、純粋な贈与する者である「存在」との間にくりひろげられる、かぎりない対話のプロセスそのものだ。
・D・H・ロレンスも大地を貫流する「贈与の霊」への予感に、うながされている。
「Not I,not I,but the wind thar blows through me」。
私のなかを吹き抜ける風が、書いたのだ。「私」がそれを書いたのではない。
・人間の心に、不信や相手を支配しようという欲望が発生した瞬間に、この風は動きを止めてしまうのである。
贈与はいっさいを先送りする。それは対話の状態をつくりだすが、
相手に自分の考えや欲望をおしつけることはできない。
贈与の空間には、無限の深さがあって、その空間を自由な霊の流れがみたしている。
つまり、それを信じなければ、贈与の大いなる環などは、
存在もしないし、動きだしたりもしないものなのだ。
・人類は「死への恐れ」につきうごかされて、農業をはじめた。
財産はたしかなものとなり、所有は堅固な形式をもつようになった。
そして、そのかわりに、自然との契約の精神を失いはじめた。
農業には「死への恐れ」、所有の喪失への恐れが潜在している。
ここから商業の世界までは、一歩なのである。
・(ミダス王の物語)貨幣は大地を殺す、とこの神話は語っているのである。
ディオニソスの贈与は、大地が持っていた贈与する能力を殺害するのである。
自然の贈与によって、「無」から「有」の発生が可能になる。
ところが、貨幣は、「無」から「有」をつくりだす能力をもっていない。
「有」を別の「有」に変態させることができるだけだ。
そのために、貨幣の登場によって、贈与の霊は致命的なダメージを受けることになる。
・貨幣が社会の富を貯蔵し、流通させる手段として発達するようになると、
人間の生きる世界の底部では、いっせいにあの「充溢した無」の領域への開口部が閉じられはじめるのだ。
・貨幣の出現を準備したものは農業である。
・貨幣にいたって、「死の恐れ」に対処しようとする欲望は、
完璧な表現のかたちを見出すことになる。
ミダス王を飢え死にさせようとした貨幣は、それ自身が死の様式としてできている。
つまり、貨幣による経済の発達は、死の様式によって、
「死の恐れ」をのりこえようとする試みだった、といえる。
・貨幣には、自分自身の形というものがない。
いわば無形の流動体だ。その流動体が、交換されることで、さまざまな商品に姿を変えていく。
品物などはうつろいやすいものだ。形あるものは、滅びる。
だが、無形の流動体に姿を変えた価値は、めったなことで消滅 しない。
いったん価値としてこの世にあらわれたものは、貨幣の変態することで、
不滅の身体を獲得することになる。
その身体は形をもっていない。
しかし、それが「有」世界の、頑丈な底部をつくるのだ。
・この世界では、すべてが「有」から出て、
別の「有」へたどりついていくプロセスとして、できあがる。
財産の存在やその所有に死をもたらす「無」が侵入してくることはめったにない。
商品の世界は、「死への恐れ」につき動かされながら、
ついに価値を消滅から救う、有力な方法をみいだしたのだ。
・コンピューターはいちど人間の脳に浮かんだ知識を、
いつまでも「有」の世界の中にとどめおくために、
きわめて短期間のうちに急発達をとげた。
私たちは、ここにも「死への恐れ」の新しい形態を発見できるのである。
・豊かなこの世ならぬ「無」から贈られたものであったものが、
こうして「有」の世界に捕獲され、そこでたしかな財産につくりかえられる。
そして、人々はそれを消費しながら、そこにかすかに残された「無」の残響を聞き取るのだ。
(Not I,not I,but the wind thar blows through me……)
「すばらしい日本捕鯨」
・捕鯨は日本の漁師たちにとっては、
人間のコントロールをこえた不可視の領域である海の中から、
その海と一体であるような巨大なからだと知性をそなえた生き物を引き上げる、
そのスリリングな移行の瞬間にかかわる技術にほかならなかった。
・その移行をつうじて、神は人間の世界に食料としての富を与え、
逆に動物のたましいは仮面から解き放たれて、神の領域にもどっていった。
その変化がここでおこった。表象は富であり、たましいであり、
切断面であり、移行に運動であり、仮面がそれを統一する。
そして、人間の世界へその仮面のあらわれ、表象のあらわれを実現するのが、
狩猟の行為なのである―と狩猟民の普遍経済学は語ろうとしている。
・鯨が人間の駆使する技術と戦術とによって、海の底からひきだされてきたとき、
そこには境界面を横切ってあらわれた巨大な富が出現するのだ。
だが、その瞬間には、その富はまだ交換も不可能ならば、対象化もできない。
まさにピュシスのまとう巨大な仮面として、
とどろく轟音とともに、人間の前に出現する。
捕鯨は、海中から表象の原初をひきだすための技術にほかならないのだ。
・狩猟のことを、生産する戦争とよぶことができるかもしれない。
・日本における捕鯨は、海が平和の空間につくりかえられる、
そういう変化の中から生まれたのである。
海は、もはや戦争による表皮や略奪ではなく、
生産がおこなわれる空間でなければならない。
発達した海の戦争の技術は、いまや生産のほうにむかわなければならない。
生産のための戦争の技術。それは新しい「狩猟」の誕生を予告する。
・捕鯨猟民たちが、鯨の中にしばしば「神」のあらわれを感じとっていたのは、
捕鯨をとおして、彼ら自身が、鯨の生命の背後にある、
見えないピュシスの活動に直接的に結びつけられ、
それを実存的に認識することができていたからにほかならない。
日本人の技術思想の、もっとも純粋な形態のひとつが、ここにあらわれている。
・ピュシスの力は、黒い巨大な鯨の肉体となって、
人間の世界に浮上した何かがこの瞬間に、決定的な変化をとげる。
この瞬間から、物質化された富をめぐる捕鯨の資本論がはじまるのだ。
・富が平和の中だけからからは、もたらされないこと。
平和の中の富や繁栄は、存在の最深部でくりひろげられている、
戦争や狩猟や神聖な儀式におけるたたかいや厳粛な死の回路をとおして、
はじめて人間の前にあらわれてくるものだということを、
勇魚取りの漁師たちは、知りぬいている。
商品としての富、記号としての富は、人間の物質の暮らしを豊かにはする。
しかし、それは人間の目を曇らせ、富と表象のプライマルをおおいかくそうとする。
その上に、近代の捕鯨産業が、打ち立てられる。
そこでは、鯨は最初から、ただ油を抽出するためだけの、
つまりは人間の具体的な労働の中から貨幣が抽象されてくるのと同じ構造をもった、
抽象の運動のための、対象物としてのあつかいをうけている。
そして、それは日本捕鯨のような繊細な技術を滅ぼすのだ。
日本思想の源郷」
・自然と人に、「道」(秩序)をあたえるものが、太陽としての神なのだ。
・「機前(きぜん)」と呼ばれる、無と現象のはざまの、
あらゆる現象がいまだ未発の状態にある、不思議の内にあるというのである。
「機前」の中にある神は、この世界のいっさいの生成の根源の神でありながら、
しかもこの世界には所属していない。しかも、その神は超越の神ですらない。
超越の神というのは、言語の中に内蔵されている超越機能の、極限にあらわれてくる概念だ。
ところが、この「機前」にあっては、未発の中にあるものを、
現象の世界にひっぱりだしてこようとする、言語の超越機能が、
いっさい働いておらず、すべては「おのずから」スポンティニアスに、
無の中から動きを発生させているのである。
「バスケットボール神学」
「ゴダールとマルクス」
・生殖にとっていちばん大切なのは、じつは性器ではなくて、頭なのだ。
子孫をつくる生殖力の「種子」は、頭に宿る。古代ローマ人にとっては、
子孫は頭(Caput)によって、増殖していくものだった。
・カプート―キャピタル―キャピタリズム。はじめから、ことは、増殖にかかわっていたのである。
・百粒の小麦種が千倍に殖えるプロセスは、けっして等価交換ではない。
ここでは、交換とは異質な何か、すなわち「贈与」がおこっているのだ。
このことに気づいたフィジオクラット(重農主義)は、
「純生産物」をもたらすその力の存在を、
「純粋な自然の贈与」(don pur de la nature)と命名している。
このとき、大地は自然のCaput(頭部)であり、
それはCapitalとなって、増殖をつくりだす。
それは、交換ではなく、贈与をとおして、人間の世界にもたらされる。
ピュシスは純粋な生産力として、きまった形態をもたない。
その無形な抽象的な力が、植物の生命システムを通過して、物質化だれる。
生命システムが、ピュシスに物質性をあたえる変換の場として働いて、
そこに生産がおこっているのである。
そこに増殖がおこり、人間はその富を、自然からの贈与として受け取るのだ。
・農業の観察をとおして、フィジオクラットは、
近代世界というものの持つ「二重性」の本質を、はじめてはっきりと認識したのである。
近代の経済社会は、等価交換を原則として組み立てられなければならない。
そこでは、等しい価値と価値、等しい意味と意味が、交換される。
つまり、論理学が、言葉によって真理を表現するときに、
必要な条件としてとりだした原則のすべてが、
経済の領域にも貫かれていなければならないのだ。
しかし、同時に、この世界は、年々歳々、巨大な富の増殖をつくりだしてもいる。
この増殖は、原理から言って、等価交換という「ゲームの規則」からは、
生まれないはずのものである。
・「彼の蝶への成長は、流通部面で行われなければならないし、
また流通部面でおこなわれてはならない。これが問題の条件である。
ここがロドスだ。さあ跳んでみろ」(『資本論』)
・私たちの生きている資本主義社会でも、
まぎれもない余剰価値の発生が、おこっているのである。
それは、資本家が労働者から物質化された商品を買わないで、
労働力自身を買うことから生まれる。労働力は、それが生産する物よりも、
小さい価値しかもっていないからだ。
なぜならそれは抽象的なピュシスの力として、
またヴァーチャルな空間を生きているものであるから、
その力が顕在化してつくりだす物よりも、
この社会では、小さな価値づけしかあたえられないからである。
資本家は、ヴァーチャルな力を価格どおりに買うことによって、
物質に顕在化された世界に、余剰価値を発生させることに、成功したのである。
等価交換という「ゲームの規則」を少しも侵害することなしに、
しかも、豊饒な大地のあたえる「自然の贈与」なども必要としないで、それは実現されたのだ。
・「貨幣の資本への転化」とは、
「存在者の存在への転化」という驚くべき事態の、
ネガティブな表現にほかならない。
「貨幣の資本への転化」というネガティブな表現を、
この社会のうちを生きながら、瞬間瞬間に、
そのポジティブな裏面である「ピュシスとしての存在の顕現」につくりかえていくこと。
「バルトークにかえれ」
・バルトークの作曲したピアノ曲「夜の音楽」(組曲≪戸外にて)の第4曲)は、
おそらくあらゆる「夜の音楽」の中でも、もっとも近く、
この生命と死との境界面上に接近させていった驚異的な作品だ。
・バルトークの「無神論」は、ニヒリズムとはまったく縁がない。
彼は、個性体のうちに閉じ込められる「魂」の永続などは否定したかわりに、
個体的な生命をこえて、宇宙を貫流しつづける生命的な力のほうに、
自分の知性を、開いていくことができた人なのである。
・生命を生命たらしめているもの
(それは個体的な生命をつらぬきながら、その限界をこえ、流れつづけるものである)、
存在を存在たらしめているもの
(それは個々の存在物の存在を、あらしめているものである)
にたいする、圧倒的な実在感を、いだいていた人なのである。
生命を生命たらしめているもの、存在を存在たらしめているものを、
古代ギリシア人にならって、「ピュシス」と呼んでみることにしよう。
・生命は、多様な豊かさを生む、ヴァーチャルな可能性の空間なのである。
・フロイトはそれを「エス」としてとらえようとした。
エスは無意識の領域で活動をつづける、生命的なプロセスであって、
たんに「それ」としか表現のしようのない、不気味な抽象性をもった活動力なのだ。
意識や前意識の活動は、このエスを抑圧したり、
カオスに目鼻をつけるような改造をほどこすことによって、なりたっている、
仮構のシステムにほかならない。
エスは意識活動のどこにも局在してあらわれることはないが、
意識の活動のあらゆる部分をつらぬいて、たえず流れつづけている。
精神分析学は、フロイトにとっては、
エスのかたちをとったピュシス的なものの探究の学問として、
構想されている。
・音楽との接触面に近づいていけばいくほど、
言語の構造性は、解体にさらされていくが、そこにポエジーが発生するのだ。
詩の言葉は、まるで「夜の音楽」のように、
宇宙的なもの、ピュシス的なものへの接近を、こころみているのである。
・「音楽は、あらゆる芸術の中で、もっとも狂気に近い」(ロラン・バルト)
・言葉は音と意味とのふたつのレヴェルでできている。
そのために、純粋な音のレヴェルを離れて、意味のレヴェルに移行すると、
もうピュシスの動きに、直接触れていることはできなくなってしまう。
ところが、音楽はその全身のあらゆるレヴェルをもって、
ピュシスに直接的に触れたまま、
それを人間の感覚的知性の内に、開き、立てることができる。
このとき人間は音楽をとおして、世界を了解するのである。
「新贈与論序説」
・「構造」とは、じつに不思議な概念だ。
「構造」は、無に内在していて、
その無が有に移行する境界の領域で、
ある物質性をおびることになる。
そのために、有のなかには、その「構造」の痕跡が残ることになる。
だが、当の「構造」そのものは、「絶対的に独創的なもの」として、
夢と同じように、実態を持つものとしてとりだすことができないしろものなのである。
・レヴィ=ストロースはそこで、
価値や意味の運動をつき動かしている、
「贈与の霊」と呼ばれているその力のことを、
抽象的に「ゼロ記号」と呼ぶことにした。
この「ゼロ記号」は、それ自身ではなんの意味も価値もになっていないが
、それが存在しているおかげで、システムの全体が働くことのできる力の場だ。
それは、言わば、「無」であり、「霊」であり、「力」であり、
世界に対する「信」を生み出すものであり、
人間と人間、人間と自然の間に真実のコミュニケーションを発生させるものだ。
「ゼロ記号」は、意味や価値の世界の全体をささえているが、
そのシステムの中にはいあない。
それはシステムにとっての「他者」なのである。
・女性はふくよかな生産の可能性をはらんでいる。
だから、結婚によって女性が移動をおこすと、
それにつれて何かの力が動き出すのがわかる。
結婚によって、目に見える花嫁が集団の間を移動していくが、
そのとき社会の深部では、
目に見えない何かの力が円環をつくりなす運動をおこし、
それが人間の世界に、喜びを生み出した。
未来の時間に、物質化された富をつくりだしうるヴァーチャルな力能が、
女性の生命を通して、共同体の境界をこえて他方に移動をおこす。
それが結婚だ。
だとするならば、結婚の真理は、
潜在と顕在のちょうど境界にみいだされることになる。
贈与のように、あるいはシュールレアリストの夢想した美のように、
女性の生命が豊かな中間の領域を開くのだ。
・結婚において、社会に流動をつくりだしていくのは、女性である。
ところが、クリスマスの祭りでは、それを死者がになうのだ。
そのとき、死者の世界との間に、象徴的な通路が開かれる。
そしてそのことによって、
生者と死者をひとつに巻き込んだ宇宙には、
目に見えない力の運動が発生する。
クリスマスは、宇宙的な交通と対話の状態をつくりだそうとした祭りなのだ。
・クリスマスの原型である「冬の祭り」の、もっとも重要なポイントは、
生者が死者の霊にたいして贈り物をすることにあった。
それがクリスマスの基本構造なのだ。
・クリスマス祭を真冬にした決定は、
グレゴリオ聖歌の発明に、まさるともおとらない。
・死者の霊が来訪するこの霊的な季節に、
闇の中に未来の救世主の到来を告げる一条の光をさししめす、
幼な子の誕生を記念する祭りをもってくることで、
キリスト教会は、冬という季節にこめられた民衆世界の潜在的な救済思想を、
キリストへの信仰のうちに、吸収し、同化することに成功したのである。
・大人であるためのイニシエーションを受けていない者たちは、
冬のこの特別な期間にかぎって、
生者がつくる世界の「外」にある存在と、象徴的に結び付けられた。
つまり、子供と若者は、目に見えない死者の領域と、
深いつながりをもった存在として、あつかわれたわけである。
・彼らは目に見えない死者の霊の領域が、生者の世界に接触する、
ちょうど境界の面に、立っているのだ。
そのために、子供や若者は、死者の霊の欲望を体現して、
乱暴な要求をおこなう権利があったわけだし、
大人たちがつくる生者の世界は、彼らを「媒介にして」、
有体化した贈与物を、死者の領域に贈り届けることもできたのだ。
・近代の社会は、いっさいの「外」を表象化して、
自分の内部に組み込んでしまおうとする社会なのである。
・子供たちは、大人の社会の内部に、組込まれてしまったのである。
かつて、民衆の習俗の世界では、この祭りにあたって、
大人の社会と子供組は、おたがいを分離しあって、対立し、
そこに「贈与の霊」の大いなる動きがおこった。
その子供たちが、いまやブルジョワ世界というメビウスの輪の中に閉じ込められて、 クリスマスの晩が来たというのに、
おめおめと家の中の暖炉のそばで、足止めをくらっている。
子供の世界の、全面的な没落がはじまっていたのである。
・大人たちの無意識には、子供が社会の内部に組み込まれた「外」であり、
生者の世界のまっただなかに抱擁された死者の霊の仮体である、
という感覚が、生き残ってしまった
・現代のサンタクロースには、帰っていくべき無の領域などないのである。
商業主義の世界をつき動かす貨幣が、
霊とよく似た無形の流動体(ケインズは貨幣をこう形容した)でありながらも、
有から別の有への変態をとげていくことしかできないように、
サンタクロースの像をつくりだした世界は、
みずからが消失していくべき無の領域を失ってしまっている。
その世界は、無を有である自分の内部に組み込んで、
無への通路を消滅させようとする運動の中から、発達してきた。
つまり、その世界自身が巨大なファンタジーの構造としてつくられていて、
その構造の中から、サンタクロースの像がうまれたのだ。
ラカンが語っていることだが、
私たちはサンタクロースという巨大なファンタジーの中に生き、
そしてそのファンタジーを、つねに必要とする社会に生きている。
・霊と貨幣は、どちらも無形の流動体である点が、よく似ている。
それに、近代の資本主義の発達をよく調べてみると、
それがプロテスタント諸派のうちでも、「自幽霊」の働きに重点をおいた、
敬虔派クリスチャンのかたちづくる社会で、
最初の飛躍的な発達のおこったことがわかる。
この人々は、カトリックが三位一体の静的な構造の中に
おさえこもうとしてきた「聖霊」の存在を、
「自由霊」として開放しようとしたのである。
父と子のくびきを脱した聖霊は、
増殖の運動(これを「自由霊の運動」と呼んでいる人たちもいる)が、
貨幣の増殖である資本を生み出していく近代の経済運動と、
興味深い連動をしめすのである。
・ところがそのいっぽうで、霊は無への通路を開き、
貨幣はそれを閉ざして、
あらゆる存在物が有の中を際限なく自己変態をくりかえしていく世界を、つくりだした。
霊と貨幣は、おたがいに矛盾した働きをおこなうのだ。
その霊と貨幣が連動しあって、近代資本主義は生み出された。
私たちのサンタクロースとクリスマスは、
その矛盾をはらんだ運動の、もっともみごとな表現のひとつなのだ。
・商品社会が成立するためには、「もの」が商品となる以前に、
人と「もの」、人と人との間に、まずもって距離や分離が入り込んでいる必要があるのだ。
人が「個」としての分離を果たし、
「もの」が商品としての自由を獲得していないところでは、
商品社会の全能は発揮されることがない。
ヨーロッパ世界は、キリスト教によって、
その基礎をいち早くつくりだしたが、
そのキリスト教は「個」の意識を生み出すことを目的とした、
きわめて特殊な宗教なのである。
・彼(キリスト)は、この世界に「愛」の可能性を開いた。
ロゴスが世界に導き入れた分離による裂け目を、
自己犠牲の贖いによって扉を開かれたエロスの力が、
ふたたび縫合していくのである。
ヨーロッパはひとつの巨大なパラドックスだ。
見えない深層を、贖いによる愛がつなぎ、
見える世界はロゴスによって作動していく。
その両方の可能性を、同じキリスト教が開いたのである。
・まずこの儀式で、「いけにえ」として選ばれた動物は殺されることになる。
特別な空間を緊張した時間の高まりのうちに、いけにえの個体性は破壊されるのだ。
そしてその瞬間に、破壊された個体性を破って、
その内部から個体の限界から解き放たれて、
無形の流動体となった生命そのものが飛び去るのを、
人々は感知しようとしたのである。
そして、それまで個体の生命の中に封じ込められていた力が、
このとき、神に向かって返還される。こうして、
存在の世界の豊かな富を与えてくれた神に対する、
カウンター・ギフト(お返しの贈与)が果たされるのだ。
・キリスト教教理という形で、ヨーロッパが確立しようとしたのは、
イエスの十字架上の死を、神にたいして人間がおこなった供犠とみなすことによって、
社会の深層に、壮大な贈与の精神をセットすることあった。
十字架上で人類のために罪の贖いをおこなったキリストのイメージが、
それを可能にする。こうして、ロゴスの分離力によって、
合理主義と商業経済を強力に作動させてきたヨーロッパ世界の基底部には、
分離されたものをふたたび結合するエロスの原理がすえられることになった。
・「贈与の霊」はそういう個別的な物質をよりどころにしながらも、
それを越えた次元で活動する、宇宙的な力なのである。
贈与によって、人々は「もの」を交換しあっているのではなく、
おたがいの心に、そのような霊を揺り動かして、
それが動きだす瞬間をつくりだそうとしていたのである。
・ここでは、あらゆる存在や価値や意味が、おたがいに向かい合って、
呼びかけをおこなったり、対話したり、場所を移動したり、
結婚したり、別れたり、またくっついたり、子供をつくったりするのである。
贈り手と受け取り手、語り手と聞き手が、ここでは共通の領土を共有しあって、
その中でおたがいに影響をおよぼしあいながら、
未知の構造をつぎつぎとつくりだしていくのだ。
等価交換が支配している世界では、そのような「創造」は原理として不可能だ。
ものの変態はおこっても、新しい構造の創造はおこらない。
・贈与の精神によって、柔軟さとふくらみをとりもどした世界では、
いっさいのものごとはカーニヴァル的な行動を取り、
あらゆる意味と価値が、ポリフォニー的な対話を開始する。
経済学的な表現をすれば等価交換の否定、
哲学的に表現すれば還元主義の拒否、芸術の問題として語れば小説の生命、
それを倫理の言葉で語るとすれば、まさに贈与の精神にほかならない。
・私たちの考えでは、まさにそれこそが、
贈与の空間を動かしている力の「唯物論」的な表現にほかならない。
・霊も貨幣も、ともにある種の「器の破壊」を通して、出現してくる。
「もの」の具体的な使用価値の中から、
具体性を消し去った抽象的な交換価値があらわれてくるときに、
貨幣出現の準備は整えられたのである。
貨幣は「もの」の具体的な個別性を踏み破って、
その中から計算を可能にする「数」を出現させるのだ。
その結果、貨幣自身は無形の流動体と化していく。
「もの」の具体性を踏み破ってあらわれた、
この抽象的な無形の流動体は、商品社会の中では、
どんなものにでも姿を変えることができる。
同じお金が、ハムにもベンツにも、姿を変えることができるのだ。
・霊と貨幣の本質的なちがいは、ここにあるのだ。貨幣という無形の流動体は、
「無」への通路を閉ざして、人間を有限な「有」の世界の中に閉じ込めてしまう。
ところが、商業をクリティックする贈与は、人の心に霊の働きを発動させて、
「有」に閉ざされた世界に、愛の現実性を開こうとする。
近代の市場経済社会は、自由霊と貨幣との共同作業によって、その端緒を開かれた。
そして、何度かの激発のこころみのたびに、
自幽霊の働きはしだいに押さえつけられて、
いまや世界をおおいつくしているのは、反カントール的な貨幣の数字だ。
しかし、この社会の見えない奥底には、自由霊が突き動かす贈与の精神が、
いまだに静かな呼吸を続けている。だから、愛の可能性が絶えたわけではない。
「ディケンズの亡霊」
・人間は心のうちに流動する霊を持っていて、
それは生きているときに、「なかまのあいだをあちこちと出歩く」。
つまり、人間どうしがたがいに言葉を交わしたり、
理解や感情を通わせたりするたびに、目には見えない霊が流動をおこして、
個体と個体の間につながりをつくりだしているのだ。
・亡霊の出現が実現する「死者のまなざし」の獲得こそ、
人間として完成するための条件なのである
・汝の隣人を愛せよ、なぜなら神は、汝が隣人を見ているのと同じ仕方で、
背後から汝を見給うから、というわけだ。
すなわち、私が、私を見る神の視点をもって隣人を見るとき、
隣人の中に、神にとっての私の姿が見えてくるのである。
「あとがき」
・人間の霊性を主題とするこの本は、意外なことに、
その直接の源泉を、マルクスの『剰余価値学説史』に持っている。
マルクスはそこに、自分の剰余価値説の重要な源泉のひとつが、
ケネーの天才に負うフィジオクラット(重農派)の思想にあることを、
堂々たる筆致で書きつけた。
この世には価値の増殖がおこるという不思議な現象の、真に科学的な解明は、
フィジオクラットの創造になる概念「純粋な自然の蘇贈与(don pur de la nature)」によって、
はじめて可能となったのである。
・霊性というものをめぐって人類が生み出してきた広大な思想の沃野を、
フィジオクラットの経済理論をも内に包み込むところの、
極限まで拡大された剰余価値論としてとらえる、
新しい表現法の開拓にむかっていくことになったのである。