『レヴィ=ストロース―構造』
渡辺公三 著
1996年刊 講談社 <現代思想の冒険者たち 第20巻>
この本ではまずこの写真
でもこの子が
となって
と思ったら こんな落書きをしていて![]()

でもこれがボードレールの「猫」という詩に関するのかもしれないもので、
それはヤコブソンといっしょにやった構造分析のはじまりで
そこには音韻、語彙、文法云々の何とかがあるというのは
フランス語を知らないとまったくわからない…
そしてやがてこの気難しそうなじいさんの顔になっていく
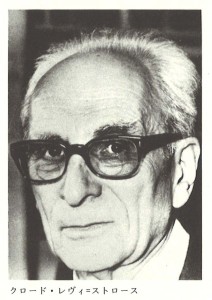 というか、枯れていく感じ。
というか、枯れていく感じ。
確かに顔の「構造」は同じはずなんだが…
という、ややマニアックな写真が並んでいるあたりからもわかるように、
けっこう詳しい解説書です。
以下、本文より
序章 構造主義のエシックス
・「『構造』とは、要素と要素間の関係からなる全体であって、
この関係は一連の変形過程を通じて不変の特性を保持する」
(1977 初来日の講演より)
・構造は同一性に文字どおり同一化し回収されることを巧に回避している
・「神話は人間の中において、人間が知らぬまに考え出される」(1977 ラジオ講演)
・「あなたが誰かであることを要求するのも社会です」(同)
・体に染み込ませた無数の神話が、たがいに共振し倍音を響かせ、
対位法を構成し、自ら新たな神話の宇宙を織りなしてゆくよう、
レヴィ=ストロース自身は、自分の身体と精神をまるでそれ自体は空虚な楽器として、
南北アメリカ・インディアンの神話に貸し与えた
・「野蛮な人々」の「地獄とはわれわれ自身のことだ」という主張には、
「世界」に対する謙虚さへの教えが聞きとれる
・「さまざまな社会の豊かさと多様性という、
記憶を越えた昔からの人類の遺産のもっとも素晴らしい部分を破壊し、
さらには数え切れないほどの生命の形態を破壊することに没頭しているこの世紀」
・こうした考え方は西欧におけるローマ帝国の法思想にも、
インドの「ヒンズー教と仏教」にも、
また「民族学者の研究対象である無文字社会」にも見られると
レヴィ=ストロースはいう。
「これらの社会は…人間を、創造物の支配者ではなく、
その受益者としている点で一致している。
これらの社会では、迷信と侮ってはならない賢明な習慣が、
人間の他の生物種の消費を制限し、
他の種に対する道義的尊重を課すと同時に、
種の保存に関するきわめて厳しい規則が設けられている」のである
・動物界および植物界は食料だけでなく「人間に一つの思考法を提供する」のだ
・何よりも自然種の多様性を優位に置き、人間の個体が尊重されるのも
それが種に類比されるものである限りでしかないという、
ある徹底した自然主義とも呼べそうな立場が表明されている。
第1章 歴史の影のなかで
・いっぽうこうした首長には、集団内での男女の数の不均衡を代価に、
複数の妻をもつ特権が認められる。
こうした事態をレヴィ=ストロースは、
集団の成員が一夫一婦制によって保証されている
「安全の個人的な要素」を、首長から期待される
「集団的な安全」と交換することであると理解する。
第2章 声とインセスト
・ヤコブソンおよびレヴィ=ストロースは、
音素がこうした小数の要素の分析できるという構造言語学の成果を、
しばしば遺伝子が小数のアミノ酸の組み合わせに還元できるという
分子生物学の成果に対比している。
・「人が話すのは、聞いてもらうためだからである」(ヤコブソン)
・「人が聞いてもらおうとつとめるのは、理解してもらうためだからである」(同)
・言語学者にとって
「機能は自明だったが、体系が知られていなかった」のに対して
「社会学者は反対の状況」にあるとされる。
・モーガンにとって制度、秩序の進化とは、
より特定化し個別化した存在を対象とするよう変容することなのだ。
人類の形成期には婚姻制度はまだ存在せず、
「原始乱婚」つまり「秩序の零度」と呼ぶべき状態が想定される。
・親族関係においては、母方のオジとその姉妹であるハハ、
その夫であるチチそしてコという四者の組み合わせこそ「基本単位」であるとされ、
さらにこの基本単位がインセストの禁止の直接の結果として根拠づけられる。
・インセストの禁止と、交換としての親族関係の成立は同時的なもの、
あるいは端的に、同じことなのである。
・「複合構造」とは、親族の範囲を限定するだけで、
通婚対象の選択を経済的な理由や心理的な理由など
親族関係以外の機構に委ねるという、
アフリカやヨーロッパなどに見られる体系を指している。
・人類学における「構造」の観念が最初に徹底して検討された親族関係の領域では、
「構造」は三つの方向から探究される。
すなわち第一に、女性の授受という広い意味での交換行為が
人間のどのような精神構造によって成り立つかという意味での「精神構造」。
第二に、交換行為としての通婚関係が
オジ、チチ、ハハ、コといった個人間の関係を
どう形成するのかという「関係の束」として構造。
第三に、交換関係が集団のカテゴリー間の関係として表現される「社会構造」
・クラスが社会全体での通婚可能なカテゴリーを明確に示す
「包括的な(総体的な)」規則を表すのに対して、
交叉イトコ婚はある個体にとっての個別的な通婚可能範囲を
緩やかな形で示すというように、
それぞれが互酬性の原理の異なった表現となっているからである。
つまり「二つの制度は、結晶化したものと柔軟なものの如く対立している」。
・「すなわち、親しく愛情にみちた気のおけぬ間柄、
給付と反対給付という互恵的交換から結果する関係、
そして二つの相互関係に加えて、
一つは債権者の態度に対応し、他は債務者のそれに対応する。
・レヴィ=ストロースは、、「人はみな親族として生まれる」という
普遍的な事実を、他者とのコミュニケーションに可能性から導き出した
・交換論を軸とする親族関係の解読は、
こうして近代人類学における親族関係論の核心を暗黙のうちに形成してきた
氏族あるいは家族を枠組みとする「同一性への問い」とは異なる地平に自らを位置づけて、
コミュニケーションすなわち交換という他者との関係が
どのように親族関係を形成するかを問うたのである。
・『親族の基本構造』の基底には「自分とは何者か」という
自己同一性への問いを強く意識した主体ではなく、
他者への開かれた交換の主体のヴィジョンがある。
・交換の体系は、ある整合性を備えたとき、
無意識のレベルに根をおろしていると見なされた組織原理によって統御される。
第3章 旅の終り
・レヴィ=ストロースは、収斂の過程に、
時間と地域を越えて歴史のなかで働く普遍的な精神のメカニズムを見ようとした、
と言うことができるだろう。
・そうした多様な条件の協働が、
人類発生以来行われてきた人類史というルーレット・ゲームにおいて、
新石器時代には世界のいくつかの地点で並行して生起し、
また近代においては2000年以上の停滞を経験した後の西欧を中心に生じたという。
・そこで対置された文化相対主義と自文化中心主義、
偶然の集積としての歴史(ルーレット)と完成への過程としての歴史(パズル)、
歴史主体の不在と西欧という唯一の歴史主体といった一連の対立する観念群は、
歴史の主体とその「他者」という、
今日まで影を投げかける近代史の基本的な争点の要約なっているといえるだろう。
・幼児にとって「『私』という代名詞が、
それのもちうる一切の意味をこめて習得されるのは、
他人たちから『お前』と呼ばれている彼自身も、
やはり『私』ということができるとわかった時なのです」(メルロ=ポンティ)
・「わたしが≪自我」から出て、ある存在と生きた関係を結ぼうとすれば、
私はどうしても≪あなた≫と出会うか、さもなければ≪あなた≫を設定することになる。
それは、わたしのそとにおいては、想像しうる唯一の≪人称≫なのである。
この内在性と超越性という特質は固有のものとして≪わたし≫に属するものであり、
しかもそれは≪あなた≫に入れ換わる」(バンヴェニスト)
・先祖の時代からそうしてきたという答えに見られるとおり、
社会習慣には合理的説明がなく、
説明が与えられる場合には二次的なこじつけに過ぎないという、
調査経験に裏打ちされたボアズの見解
第4章 神話と詩のあいだに
・『親族の基本構造』の提起した「交換する主体」は、
サルトルの「歴史に捧げられた実存的主体」、
メルロ=ポンティにおける「世界へ開かれた身体としての主体」、
構造言語学における「微細な言語の構造によって導き出される主体」、
ラカンの「無意識によって構造化された主体」などと
波紋を交差させながら、戦後のフランスの思想の世界に参入した。
・西欧社会は個人が自分自身をトーテムとして祭り上げるトーテミズム社会
・フランスは、フロイトの『トーテムとタブー』の描く
「原初の父殺し」を彷彿とさせる、 「フランス革命」における「王殺し」の血から誕生した市民=主体が、
フロイト理論をなぞるように、殺されたトーテム=王に同一化してそれが小さな王となり、
歴史の担い手として権利上は全能をもつ比類のない社会でもある
・レヴィ=ストロース自身が親族関係すなわち「人」から
神話を通じて「世界」へと関心の焦点を移し、
『神話論』では、「人」は何よりも「世界」の内部に生きるものとして、
世界に織りこまれた存在として問われることになる。
・重心の移動の過程で、「人」「世界」を相互浸透の緊張に満ちた均衡点でとらえたのが『野生の思考』の考察だった
・作者もオリジナルもないテクストが存在するというヴィジョンは、
西欧における文学批評深く持続的な衝撃をあたえることになった。
・レヴィ=ストロースの視点の新しさは
神話がラングに対比される可逆的時間性をも備えた「構造」であるという指摘にあった。
言い換えれば、神話が何かを語り伝えるといういわば自明のことに対して、
その何かが「いかにして」語り伝えられるのかを明らかにしようとしたのである。
・神話がこうした関係を表示する「文」すなわち「神話素」にいったん分解され、
時間軸に沿って左から右へ出来事の経過として不可逆に、
上から下へ出来事の対比の関係として可逆的にも読める形で
マトリックス(行列式)として配置された時、神話分析の作業は始まると考えられる。
第5章 幻想から思考へ
・こうして着想された批判によって、トーテミズムは、
人間に関わるいくつかの現象を分解して恣意的に組み立て直す、
19世紀末の科学に共通の傾向の生んだ幻想として解体される。
・種の系と氏族の系の対比は、レヴィ=ストロースによって
「自然」と「文化」と呼び替えられ、これら二つの系の対応が問題とされる。
・古典的な定義は動植物を「食べる」ことの禁止を重視したが、
二つの系の関係を全体として見れば(そして全体として見なければならないのだが)、
自然種は集団の「隠喩」として使われている
(自然種相互が異なっているように集団同士も異なっている)。
・「野蛮人とは野蛮が存在すると信じている人のことだ」
・『親族の基本構造』からさらに踏み込んだ『野生の思考』のモチーフは、
こうした社会集団のカテゴリーそのものが、
種を思考の媒体として構成されるものであるとすれば、
交換の体系という枠だけには収められない、
比喩を活用した思考の変換の体系として把握できるのではないか、
という点にあったと思われる。
・「関係づけ」という思考活動の基礎を、
自然の種すなわち生命形態の差異と多様性がどのように誘導し解発し形を与え、
そしてそれによって思考が何に答えようとするのか、という問いを立てた時、
それはすでにトーテミズム幻想の批判というネガティブな作業の範囲を溢れ出て、
新たな質の探究の場を開いている。それが「野生の思考」であった。
・◇まずこの議論全ての基礎として、人類学者が観察し報告してきた
「野蛮人」と呼び捨てられてきた人々自身の
自然の生命形態の多様性への関心のあり方を、
先入観なしに性格に理解しなければならない。
・◇こうして明らかにされる自然認識は人間の存在において
どのような意味をもつのか問わなければならない。
言い換えれば、種の多様性を媒体として用いる思考体系には
何らかの目的論が内包されているのか、という問いが立てられる。
・◇右の問いとも関連して、具体的な操作媒体によって運用される「野生の思考」と、
近代科学を生みまたそれによって育てられた「栽培された」思考操作との
違いと共通点を明確にしなければならない。
・その知は目的達成のための効率の計算に方向づけられた、
狭い合理性に基礎を置くものというよりも、多様性が目覚めさせる感性的な喜びへ、
いわば「種の詩学」へと方向づけられたものなのだ。
そこでは感性的なものが、損なわれることなく理性の領域に統合されていると想定される。
・知的な好奇心と詩的な喜びに導かれた
多様性のたゆみない識別とそれに誘導された思考こそが、
植物の栽培化や動物の家畜化、機織りや土器作りなどの文明の技術の創造を可能にした、
とレヴィ=ストロースは言う。
・レヴィ=ストロースによれば
「同じ材料を使って行うこのたゆまぬ再構成の作業の中では、
前には目的であったものが次には手段の役にまわされ」、
意味するものが意味されるものへ、意味されるものが意味するものへと替わる。
現代の科学や狭義などのゲームが、
法則や規則という「構造」から「出来事」を生み出すのと対照的に、
神話や儀礼は「出来事の集合を分解したり組み立てなおしたり
…交互に目的となり手段となるような構造的配列を作り出そうとする」のである。
・それが外的な制約なしに、内的な制約だけにしたがって
「世界」をじかに媒介してイマージュの構造体を作り上げるとき「神話」が生成する
・親族関係論においては社会構造は交換の体系
すなわち人間における他者とのコミュニケーションの必然性によって基礎づけられた。
『野生の思考』はこうした人間における
他者とのコミュニケーションから生じる帰結としての社会構造を、
人間が自然種、いいかえれば自然の生命形態の多様性を
手段として作り上げる思考の体系から引き出そうと試みる。
それはいいかえれば人間の世界のなかで
閉じたコミュニケーションの体系を解きほぐして、
人間と自然とのコミュニケーションのなかに解き放ちそこに包摂する
という試みなのである。
・種操作媒体が、適用できる領域は
「トーテム・クラン(氏族)」としての人間集団のみには限られない。
むしろトーテミズムの幻想こそ
「野生の思考」の「社会」への適用という一面だけを分離できる
という誤った前提の上に成立していたのだ。
・カーストという「社会構造」の最たるものもまた、
人によって「生きられた分類の論理」として
種操作媒体からの変換のひとつと捉えることができる
・種操作媒体は柔軟な媒介能力によって
「網目を広げて…元素、範疇、数の方へ向かう」こともでき、
「網目を細かくして項有名詞の方へ向かう」こともできる。
そのことを明らかににして初めて
「生きられた分類」の論理の全体像に近づくことができよう。
・いずれにせよ少なくともレヴィ=ストロースの考察は、
人間がこうした他の生命形態と親密な関係をもって世界を構成し、
名という媒体を通じつながっている限りで、
人間の存在は裸形の個体制にまで還元されることなく、
自然にとりまかれ、自然の種との交通のさなかに生きることが
可能であることを示していると理解されよう。
後に『神話論』の終巻に付される『裸の人』という標題も
そうした自然と交流する存在の形象として用いられている。
・それは人間を自然と分離せずに常に自然へと送り返し、
種の多様性によって同一種としての人間内部の多様性を表現する
・種による分類の論理は種のさまざまな特徴をひきだして
常に放射状にイマージュの網の目をひろげる動的な性質をもつ。
・「野生の思考」における「同一性」とは
わたしたちの既成の概念とは対照的に、
個人の個人としてのかけがえのなさといったものに収斂するのではなく、
個体の常なき変容と、異質なものの出会いの場としての個体の可能性を意味するのである。
・人間が「種の多様性」によって思考の可能性を開かれた時、
こうして思考のなかに宿った個人の意識あるいは主体の意識とは、
思考の側から見れば個体性の錯覚ともいうべきものであろう。
重要なのは、錯覚の根拠としてのさまざまな出会いの個別性ではなく
「種としての個体」においてさまざまな出会いが起こるということ自体なのだ
・「私が「野生の思考」といっているものは、
それによって「他者」を「わたしたち」に翻訳したり
またその逆をおこなうことができるような
あるコードを作りだすのに必要な前提や公理の体系であり…私の意図においては、
彼らの位置に自分を置こうとする私と、私によって私の位置に置かれた
彼らとの出会いの場であり、理解しようとする努力の結果なのです。」
・いずれにせよ、こうした努力が、個体の個体性に代えて
「種としての個体」を見いだしたことと、
レヴィ=ストロースの探究のこの段階において
「社会」の次元が限り無く不在に近くなること、
そして一見すると歴史に残された場が切り詰められることとは互いに連関している。
・「あなたが誰かであることを要求する」社会から離れ、
自然の間近で語り出される神話に耳を傾けることは、
そのままあらゆる「歴史」を否定することではない。
第6章 新石器のビルドゥングスロマン1 ―南半球の森から
・人間の成長とは、とりもなおさず人間がこの世界に織り込まれてゆく過程でもある。
後に見るとおり「感覚的なもの」や「形態」の対立などによって語られているのは、
「火の起源」であり「水の起源」であり、また(少なくとも煮たものについては)
火と水が与えられて始めて可能となる「料理の起源」であり、
料理を知ることによって人間が「自然状態」から「文化の状態」へ
移行したという事実なのである。
・「自然から文化への移行という大きなテーマをめぐっての変奏曲」
・それを語る人々の居住地の緯度を調べ、その位置における星座の動向を確認し、
降雨の年間分布と引き比べつつ、さまざまな異伝を対照し、
神話の細部を解読するレヴィ=ストロースの考察の行程は、
あたかも神話に、この宇宙の微細な運動を写し取り、
それに言葉を与えることで人間にもそこに参与することを可能にするための、
生命ある物質系という知的な装置あるいはコンピューターにも似た
何かのイマージュを見ようとしているかのように思える。
・物的で生命活動に満ちたこの世界を
宇宙と呼ぶのもまだあまりにも抽象的すぎるかもしれない。
「世界はなぜかくあるのか」という問いには、
始原の言葉によって答えなければならないということを認めれば、
それがなぜ神話として語られるのか納得される。
第7章 新石器のビルドゥングスロマン 2 ―北半球への旅
・数万年というきわめて息の長い尺度で立証された
南北アメリカのインディアンの移住の歴史と、
ある文化的な共通の基礎を前提として、
ふたつの大陸にまたがる規模で神話を比較するという試みは、
その壮大さと細部への捜査の緻密さにおいて、
レヴィ=ストロースが常に敬意をもって名を引いているデュメジルによる
印欧神話の比較研究を別にすれば、今世紀でおそらく空前絶後のものであろう。
終章 「構造」の軌跡
・それは同時に、彼らの歴史がどのようなものあり、
彼らの歴史と「文明」世界の歴史がいかに異質であり、
「文明」世界が自らの歴史をいかに彼らに強制してきたか、
ということへの問い直しでもあった。
すでにふれたように「彼らの」歴史への関心は
ブラジル滞在当時から、『ブラジルへの郷愁』にいたるまで一貫して持続されている。
・「同一性もまたそれ独自の不確実な関係をもっているとみなしうるのだとすれば、
わたしたちが未だにそこに付与している信仰は、
たかだか数世紀しか持続しない文明のあり方繁栄でしかないということも
ありうるのではないだろうか。
そうだとすれば、あのわたしたちの耳をそばだたせている
有名な同一性の危機は、まったく異なった意味をもってこよう。
それはわたしたちのちっぽけな人格のそれぞれが、
自らを本質的なものと取り違えることを放棄するという地点に近づきつつあることの、
心暖まる、幼い徴候とも見えてくるだろう。
本質的なものとは、すなわち実体的な現実ではなく不安定な機能であり、
協同と交換と闘争との同じように束の間の場と契機であり、
そこにはその都度微分的な差異をもって自然と歴史の力だけが、
われわれの自閉的状態にはまったく無関心に関与しているのである。」
(レヴィ=ストロース『同一性』)
・おそらく新石器時代人とは、余りに近現代的な「主体」という呪縛からも、
宗教的な信仰といった個別的な伝統の束縛からも、
歴史という制約からも、機械論的な科学のドグマからも自由な様式のもとで、
いいかえれば感性の領域と理性の領域が切り離されることなく、
世界との接触に五感をあげて動員されていたと想定されたイマージュに他ならない。
・こうした森に営まれる生命の多様性との
五感をつうじたコミュニケーションの可能性の再発見こそ、
そしてその可能性を基礎として、自然のなかでの人間の位置を問い直すことこそ
構造主義に内包された、強くまた明確な方向だったのである。





“『レヴィ=ストロース―構造』渡辺公三 著 1996年刊 講談社 <現代思想の冒険者たち 第20巻>” への1件のフィードバック